
船舶管理業務特集①船舶の安全運航を支える船舶管理の最前線
船舶管理業務は、船舶を運航するために必要な船員の配乗、海図や船用品の調達、船体や機器のメンテナンス、必要な資格証書の取得など多岐にわたり、船舶の安全運航に欠かせない役割を担っている。本特集では、船舶管理業務を行う企業へのインタビューを通じて、船舶の安全運航の最前線にフォーカスする。第1回目は、国内有数の鉄鋼原料輸送を担う海運会社、NSユナイテッド海運の船舶管理業務の現状について、同社の船舶管理業務担当者に話を聞いた。
NSユナイテッド海運は、鉄鋼原料の海上輸送における高い専門性を持ち、原材料・食料・製品・エネルギー資源の海上輸送における総合力を兼ね備えた国内有数の海運会社である。2024年3月31日時点の運航船は外航133隻、内航83隻。
同社管理船は30隻。船舶管理業務は、安全管理グループと船舶管理グループが担っている。安全管理グループは、いわゆる海務業務や船員業務を担当しており、航海士・機関士共に配属され、本船の運航サポートやマニュアル整備、船員管理や教育などソフト面の業務を行っている。一方、船舶管理グループは工務を担当し、主に機関士出身者が船舶修繕資材やドックの手配などを行っている。
本インタビューでは、同社の安全管理グループに所属する磯部 文氏、久保 綾乃氏の2名に話を聞いた。2名は航海士として乗船経験を持ち、2024年に海上職から陸上職へ異動した。
安全管理グループ
| 安全・品質管理チーム | 磯部 文 氏(写真 左) |
| 船員チーム | 久保 綾乃 氏(同 右) |

――安全・品質管理チームの業務内容についてお聞かせください。
磯部氏:安全・品質管理チームでは、船舶検査(以下検船)業務や会社のマニュアル作成を行っています。検船とは、船舶の安全性や規則への適合を確認するための検査を指します。運航船舶がPSC(Port State Control、寄港国による船舶の検査)などで指摘を受けることなく円滑に航行出来るよう、当チームにて内部監査を軸とした検船業務を行っています。
また、会社の安全管理マニュアル(以下SMM)の作成や改定も行っています。船を運航する際、例えば狭水道航行時や、閉鎖区域での作業などリスクを伴うものについて、作業マニュアルや手順を会社が定め管理船舶に遵守するよう通知しています。これら当社の安全管理システム(SMS)が現状に合ったものに保たれるよう、変わりゆく規則(条約)や業界の求める手順を考慮し、タイムリーに改廃や追加を行う事でSMMの適切な管理を行っています。
最近では、IACS*統一規則の発行を受けて、サイバーセキュリティに関する手順をマニュアルに取り入れました。本船上でのパソコン・周辺機器の取り扱いに関し、全船に周知しているところです。
*IACS (International Association of Classification Societies; 国際船級協会連合)
その他、船からのトラブルやPSC等の外部検船で不備を指摘された際、対応する部署をSMMに従い振分け、トラブル後の円滑な是正や再発防止策を策定する業務の事務局としての役割も担っています。
海務チームや保船チームでは、一人の監督の担当する船が割り当てられていますが、当チームでは担当船が決まっているわけではなく、チームマネジャーを含め7人全員で全管理船30隻の内部監査や外部検船の対応を行い、時には営業の要請を受け当社用船のサポートをしています。
――船員チームの業務内容についてお聞かせください。
久保氏:船員チームは14人で、そのうち外部管理船を含む約40隻を配乗担当者8人で受け持っています。船員チームは、船員配乗のほか、船員の傷病事案の対応や、労務関係の業務などを行っています。
配乗船の中で日本人と外国人が混乗している船舶が3隻で、その他はフィリピン人全乗もしくはベトナム人全乗となっています。私は主に外国人船員の配乗を担当しています。
――船員の労働環境改善において取り組まれていることをお聞かせください。
久保氏(船員チーム):船員チームでは、船員の満足度を上げる環境作りへの取り組みを行っています。労働環境の整備や、長期間勤務されている方には、勤続年数に応じた表彰やボーナス支給があります。その他、月に1度、船ごとに娯楽費を支給しており、船内でパーティーをする際の費用として使用してもらったり、数ヶ月分の娯楽費を貯めて、カラオケ器材やゲーム機、漫画やDVDなどの購入に充てている船もあります。
磯部氏(安全・品質管理チーム):本人船員の評価制度として「360度考評価」を取り入れています。上司が部下を評価するだけではなく、部下からも上司を評価する取り組みです。乗船期間を終えた後、トップ4と呼ばれる船長、機関長、一等航海士、一等機関士に対して、下位の航海士、機関士が評価をします。評価項目には、船内の雰囲気や、指示の出し方、不適切な言動がなかったかなどがあります。
他社でもハラスメント窓口などは設置されていると思いますが、能動的に動かなければ対応してもらえないことが多いのではないかと思います。その点、当社の360度評価は下船時に若手が全員提出することになっているため、会社に対して意見を伝えやすい仕組みになっています。
――現在の陸上業務において、苦労されている点や課題などはありますか?
久保氏(船員チーム):傷病案件が発生したときです。実際にケガや病気をしている船員がいるので、迅速に病院を受診できるよう手配する必要がありますが、本船が運航している地域によっては、昼夜を問わず対応しなければならない場合もあります。多くの船に配乗していますので、残念ながらそういった案件が重なってしまうこともあります。1人の担当者に負担が偏ってしまう場合は、周囲がフォローし合う体制になっています。
磯部氏(安全・品質管理チーム):文書を扱う部署なのですが、過去のものも含めて書類の数が膨大になっていることが課題です。社内には様々な手順書のほかに、各チームからの回覧も多くあります。現在はデジタル化への移行段階ですが、取捨選択や整理に時間がかかりそうです。また、社内だけでなく、船にも多くの書類があります。保管年数を過ぎたものが残っていることもありますが、処分するきっかけがないとなかなか捨てられず溜まってしまいます。
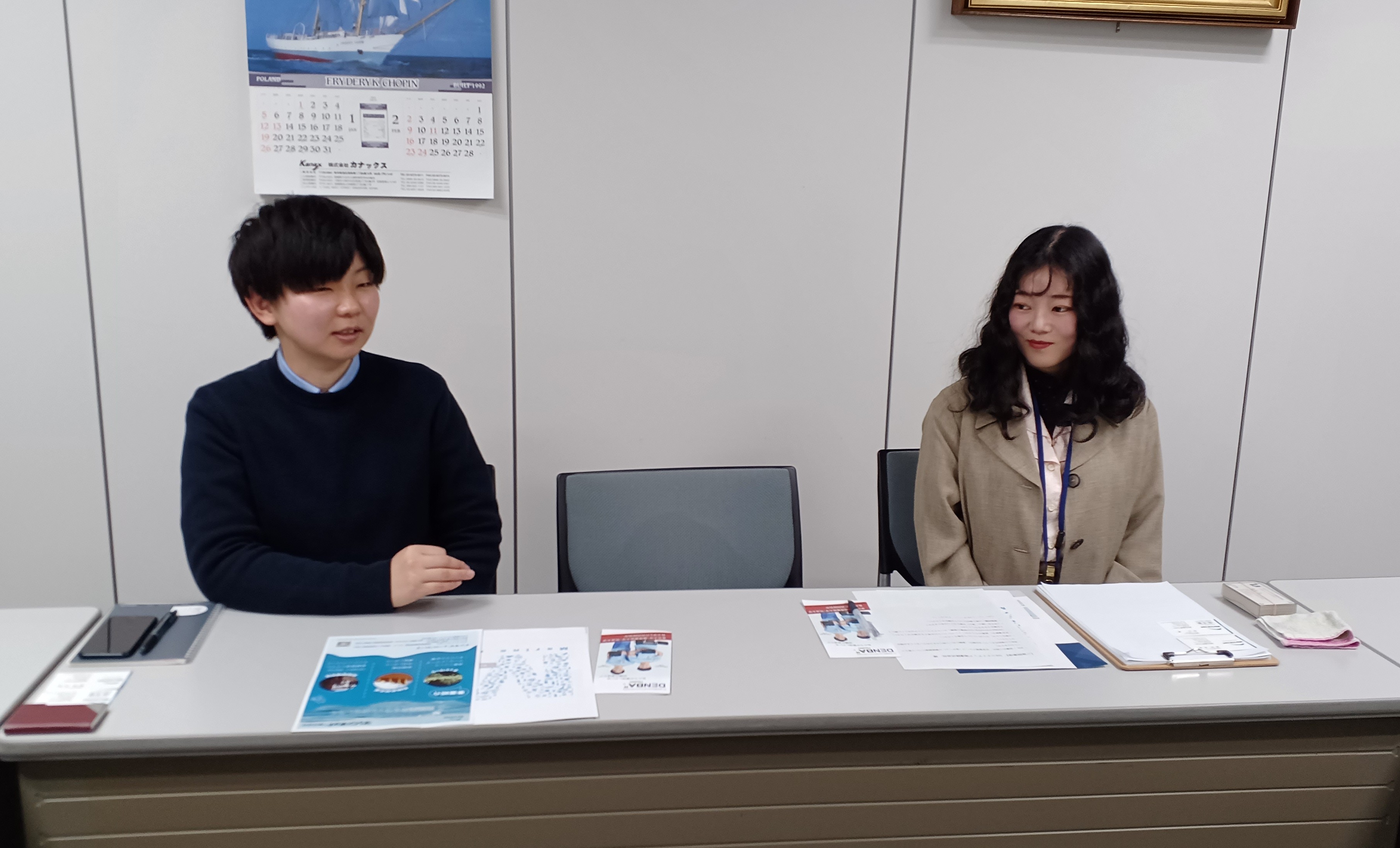
――現在のチームでやりがいを感じるのはどんな時ですか?
久保氏(船員チーム):配乗計画や様々な手配を経て、自分が担当した船員が実際に乗船する時、またその後、無事に下船して自宅に帰ったという報告を受けた時です。安心すると共に、達成感を感じます。
私は昨年まで海上職でしたので、手配される側の立場でしたが、船員チームに配属され、自分が乗船した時の状況を改めて知ることができました。また、以前一緒に乗船したことがあるフィリピン人やベトナム人の船員の配乗を手配する機会もあり、彼らが元気に活躍していることを知ると嬉しくなります。こうした経験も、仕事のやりがいにつながっています。
磯部氏(安全・品質管理チーム):チーム名の通りですが、安全・品質管理に携わることにやりがいを感じています。検船やマニュアル改定などを通して、船の安全運航や業務改善に貢献しているという実感を持てることが、大きな励みになっています。
当チームのマネジャーは、まず従業員一人ひとりの健康が確保され、最適なパフォーマンスを発揮できる環境が整った上で、品質管理の業務に取り組むという方針を示しています。私自身もこの考えには共感しています。
――お二人は昨年陸上勤務となったそうですが、配属されるチームはどのように決まるのでしょうか。
年に一度、希望部署に関するアンケートが実施されます。陸上勤務と海上勤務の切り替えは、その時の状況や本人の適性によって人事が判断し、部署割り振りが行われます。ローテーションの形で、海上勤務と陸上勤務を3~5年の周期で繰り返します。海上から陸上勤務に切り替わるときには、ほとんどの場合、以前とは異なるチームに配属され、様々な業務に関わることで船舶管理業務の全体を見る広い視野を養えます。
――貴社では、全管理船で共有スペースにスモーキングルームを設置しているほか、野菜室に食品鮮度保持装置DENBA+ Marineを導入していると伺いました。
久保氏(船員チーム):スモーキングルームは、2024年に導入されたばかりです。私たちも含め一定数の船員から、船上の分煙化をして欲しい、という要望がありました。もともとは共有スペースに灰皿が置かれており、喫煙をしない人も同じ空間にいましたが、スモーキングルームの設置により、喫煙者・非喫煙者双方にとってより良い環境が整ったと思います。スモーキングルームの設置に関しては、導入決定後に後付けで船に積み込めるものを探すのに苦労したと聞いています。既存船には電話ボックスのようなサイズのものを後から設置していますが、新造船には最初から喫煙室が設置される予定です。
DENBA+ Marineに関しては、クルーウェルビーイング向上の一環として、少しでも船上で新鮮野菜を維持できれば船員の為になるのでは、と考え採用しました。

船員の福利厚生という点では、船上で高速インターネットを利用できる衛星通信サービス「スターリンク」を管理船全船で導入しており、1人あたり月12GBまで使用できます。導入後は、船員が休日や空き時間に船上で家族とビデオ電話をしている姿や、サッカー中継の観戦をしている姿を目にする機会が増えました。またアンケートでは、「使用できるデータ通信量が増えて助かっている」という声も寄せられました。
この他、一部の船ではホールドクリーニングロボットを導入しています。船では様々な貨物を積載するため、定期的にホールドクリーニング(貨物艙の清掃)を行いますが、短期間で作業を終わらせるために、乗組員総出で作業を行うことがあります。高所作業で危険も伴うため、船員の安全確保と負担軽減のために、ホールドクリーニングロボットを導入しています。

今回のインタビューでは、船舶管理業務の中でも海務と呼ばれる領域の一部業務を紹介していただいた。インタビューを通じて、海上・陸上職どちらも経験したからこそ得られる多角的な視点が、業務に活かされていることが分かった。また、同社では安全管理に関する意識の高さだけではなく、船員の職場環境改善のための施策整備に積極的であることが印象的だった。
なお、本インタビューの続編として、同社が保有・管理する撒積貨物船“NSU ULTIMATE”の船長および乗組員の方々へインタビューを行い、船上での業務に関する話や、船員のウェルビーイングに関連する設備への感想などを聞いた。
※続編はこちら