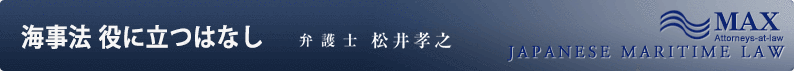
韓国でのフェリー事故 -セウォル号の賠償問題に関する法律的考察- (2/2)
船主責任制限に関する2つの大きな考え方
船主責任制限制度には、世界的に見て、大きく分けて、考え方に2つある。
ひとつが、金額主義と言われるものである。これは、船舶の積量トン数に応じ一定の割合で算出した金額に限定して船主に責任を負わせる考え方である。
もうひとつが船価主義といわれるものである。これは、船主の責任に関して、船価および運送賃を限度とする考え方である。
■責任制限法の考え方
|
現在、いくつかの国際条約が、船主の責任の制限に関して規定を設けている。大きく分けて1976年条約といわれるものと1996年条約と言われるものである。両方の条約も、船舶のトン数に応じ一定の割合で算出した金額に限定して船主に責任を負わせる金銭主義を採用している。2つの条約で異なるのは、トン数ごとの責任制限額にすぎない(1996年条約の方が責任制限の金額が高い)。我が国は、1996年条約を採用し、以下のように船主の責任をトン数により制限している。
|
||||||||||||||||||||||||||
※SDR(Special Drawing Rights) = 国際通貨基金の1特別引出権
|
一方、アメリカは船価主義を原則として採用している。アメリカという国は、海事に関しては多くの問題に関して独自路線を取っている。ただし、タイタニック号において船価主義の妥当性が問題になり、現在は、アメリカは、船価主義を若干修正している。
客船に関する責任制限
我が国では、客船に関しては、旅客クレームに関する限り、責任制限が認められていない。 しかしながら、韓国では、内航の旅客船で発生した旅客クレームでも船主の責任制限原則として認められているようである。
旅客船の責任制限額は、韓国の商法770条によれば、旅客の死亡又は身体の傷害によるクレームに関しては。旅客の定員に17万5000計算単位(計算単位とは国際通貨基金の1特別引出権をいい、日本円で1計算単位は約140円である)とされる。
要するに、韓国の法律では、旅客の定員に日本円でいえば2400万円強を乗じた金額に法律上は責任が制限されることになる。
ご遺族への賠償額に関して、責任制限がなければ仮に3000万円から3500万円だとしたら、責任制限によりご遺族の回収は大きく下回ることになる。
それでは果たして、韓国の事故で船主は責任制限をすることが可能か?
何人かの友人の韓国弁護士に聞いたが、おそらく超法規的に韓国の裁判所は、船主の責任制限を認めないであろうというのが返答であった。
法律的には次のようなロジックである。
韓国の法律では、「船主自身の故意または損害発生の恐れがあることを認識しながら無謀にした作為又は不作為により生じた損害に関しては、船主は責任の制限ができない」と規定がある。韓国の弁護士によれば、韓国の裁判所は、この条項を無理やり本件にひっつけて、船主の責任制限をシャットアウトするだろうということであった。
本件では、新聞報道によれば、積み過ぎがあったようである。また、事故時には、難所にもかかわらず、経験の浅い3等航海士が操船していたようである。船長や乗組員は、当然すべき乗客の誘導を行うことなく、真っ先に下船したようである。船員への研修費が54万ウォン(約53000円)しかなかったとされる。運航会社の清海鎮海運は近年、故障や衝突などの事故を繰り返していたらしい。社員への緊急時避難教育をしていなかったことも発覚しているようだ。セウォル号の船員全員が、船の復原性に問題があったと陳述をしているとされる。その他の船舶管理の不備、船体検査制度の不備(特に二重水密扉の作動不良)、船体改造の不備も数々と指摘されている。まさに船主への批判のパレードである。
そこで、韓国の弁護士(複数)によると、裁判所の超法規的な判断で、何らかの形で船主の不始末を韓国の裁判所が重視して、「船主自身の故意または損害発生の恐れがあることを認識しながら無謀にした作為又は不作為」があったとして、船主の責任制限を否定することになるであろうという話であった。
我が国では信じられない話であるが、船長ら乗組員に対して殺人罪の容疑がかけられている韓国の現状を見れば、そのような韓国の裁判所の判断が出されても不思議はないといえよう。 本件であるが、船体保険者は本船の堪航性に問題があったとして保険填補を拒否しているという話もある。 船長に対する殺人罪の適用やいたずらメールを発信したものへの実刑の判断など刑事裁判でも目が離せない状況である。社会的にも大きく問題となった事件であるが、法律的にも大きく取り上げられる事件になると思われる。
業務内容
■海事紛争の解決
■海難事故・航空機事故の処理・海難事故(船舶衝突・油濁・座礁等)
■航空機事故
■海事契約に対するアドバイス
■諸外国での海事紛争の処理
■海事関係の税法問題におけるアドバイス
■船舶金融(シップファイナンス)
■海事倒産事件の処理・債権回収
■貿易・信用状をめぐる紛争処理 貿易あるいは信用状をめぐる紛争、石油やその他商品の売買取引をめぐる紛争を解決します。ICC仲裁やJCAA(日本商事仲裁協会)の仲裁も行ないます。Laytime、Demurrageに関してもアドバイスを行います。
■ヨット・プレジャーボートなどに関する法律問題 ヨット、プレジャーボートやジェットスキーなどの海難事故に対処するとともに、これらの売買などにかかわる法律問題に関してもアドヴァイスを行います。
■航空機ファイナンス(Aviation Finance)
免責事項
「海事法役に立つはなし」のコンテンツはマックス法律事務所殿から提供を受けているものです。よって、マリンネット(株)が作成するマーケットレポート等、オンライン又はオフラインによりマリンネット(株)が提供する情報の内容と異なる可能性があります。従いまして、マリンネット(株)は本「海事法役に立つはなし」の記載内容を保証するものではありません。もし記載内容が原因となり、関係者が損害を被る事態、又は利益を逸失する事態が起きても、マリンネット(株)はいかなる義務も責任も負いません
著作権
•マックス法律事務所が海事法 役に立つはなし(http://www.marine-net.com/maritimelaw/)に掲載している情報、写真および図表等全てのコンテンツの著作権は、マックス法律事務所、マリンネット、またはその他の情報提供者に帰属しています。
•著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、コンテンツの複製や要約、電子メディアや印刷物等の媒体への再利用・転用は、著作権法に触れる行為となります。
•「私的使用」1あるいは「引用」2の行為は著作権法で認められていますが、その範囲を超えコンテンツを利用する場合には、著作権者の使用許諾が必要となります。また、個人で行う場合であっても、ホームページやブログ、電子掲示板など不特定多数の人がアクセスまたは閲覧できる環境に記事、写真、図表等のコンテンツを晒すことは、私的使用の範囲を逸脱する行為となります。
1. 著作権法第30条 「著作物は、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」
2. 著作権法第32条 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
Email : info@marine-net.com
