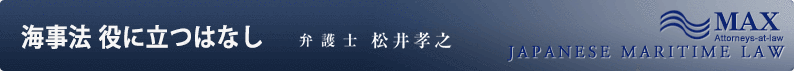
船舶先取特権に関して(特に燃料業者の船舶差押に関して)- (2/2)
我が国の法律において、船舶先取特権が認められる債権は法律で厳格に決められている。我が国では、法律に定められた債権以外に船舶先取特権を当事者で認めることはできない。
我が国の法律で船舶先取特権が認められる債権は主に以下の債権である。
| 船舶先取特権が認められる主要な債権 |
①債権者が船舶競売のために費用を支出した場合の費用
②最後の港における船舶およびその属具の保存費
③水先案内料および挽船料
④救助料および船舶の負担に属する共同海損
⑤航海継続の必要によって生じた債権
⑥船舶が其の売買または製造の後、未だ航海をなさない場合において、その売買または製造ならびに艤装によって生じた債権、および最後の航海のためにする船舶の艤装、食料ならびに燃料に関する債権
⑦雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権
⑧国際海上物品運送法が認める債権(簡単に言えば、カーゴクレーム)
⑨船主責任制限法によって責任制限の対抗を受ける債権(海難事故に基づく多くの債権がこれに該当する)
⑩造船所の工事費用
さきほど中古船の買主が船を買ったところ売主への債権者による船舶差押で憂き目に遭った話をしたが、新造船の買主も油断はできない。
最近、造船所の倒産に絡んで悲惨な新造船の買主の話を耳にした。
上記債権者リストの⑥をご覧いただきたい。
「船舶が其の売買または製造の後、未だ航海をなさない場合において、その売買または製造ならびに艤装によって生じた債権、および最後の航海のためにする船舶の艤装、食料ならびに燃料に関する債権」とある。
これは何かというと、造船所が船具業者に船具代を支払わない場合、新造船へ船具を納入した船具業者は、新造船に対して船舶先取特権を有するという規定である。
そこで、破たんした造船所から新造船を購入した買主であるが、引き渡し直前に船具業者から船舶の差押を受けて、船具代を船具業者に支払う羽目になったというわけである。
既に述べたように、船舶先取特権は、登記も公示も必要ない。思わぬところに船舶先取特権が存在して船主を苦しめることになるのである。
我が国の船舶先取特権に関して、実務上最も問題となるのが、「航海継続の必要によって生じた債権」というものである。 この債権に船舶先取特権が与えられているのは、航海継続の必要によって費用が発生した場合は、この費用は「債権者の共同の利益のために生じたものであるから保護をするのが妥当である」といういわば政策的な考え方である。
「航海継続の必要によって生じた債権」として典型的なものは、船舶が海難に遭った場合における造船所の修理費(海難工事費)であろう。
本船が海難にあった後に、造船所が修理を行わなかった場合、船舶の価値は低下するわけであり、造船所の修理は、債権者の共同の利益のため生じたものであることは明らかである。
ただし、「航海継続の必要によって生じた債権」が何かを巡っては争いも少なくない。
判例上問題となったのは、出入港に伴う綱取料、海上航行に必要な給水費、荷役に伴う費用(荷役料、ダンネージ費、検数料、税関料)、停泊中の費用(通船料、交通費その他の雑費)、船舶代理店の手数料、船長に対する貸金などである。
面白いものでは、船員が下船して飛行機で帰国した事例であるが、船員の航空機代を立て替えた旅行代理店の債権が、「航海継続の必要によって生じた債権」であるかどうかが問題となったことがある。
船舶先取特権で保護される債権の範囲に関しては、我が国の裁判所は、船舶先取特権は公示の必要がなく、しかも抵当権にも優先する強力なものであるから債権の範囲は厳格に解釈すべきであるという大原則は示しているが、ケースによって考え方はまちまちである。
この「航海継続の必要によって生じた債権」に関して特に問題になるのが、燃料油代(バンカー代)である。
数年前に香港の中堅のコンテナ会社が倒産した時に、このコンテナ会社に傭船に出していた多くの船会社の所有船が我が国で続々とバンカー業者により差し押さえられた。バンカー業者は、船舶先取特権に基づいて差押えてきたのである。バンカー代は「航海継続の必要によって生じた債権」である→バンカー業者は船舶先取特権を有する、というロジックである。月曜日は横浜、火曜日は名古屋、水曜日は大阪、1日休んで金曜は福岡、次の週は小倉という感じで続々と船舶の差押が行われた。
日本法上、典型的な事例では、バンカー代に関して船舶先取特権が認められる点はほぼ争いはないと思われるが問題は、外航船に関して日本の先取特権の法律が適用されるのかどうかである。
これは外航船特有の問題である。
パナマ船に対してシンガポールで海外のバンカー業者によってバンカーが供給されたとする。バンカーの供給契約の準拠法(解釈の基礎となる法律)が英国法だったとする。
|
まず前提として大事なことは、バンカー代に関して船舶先取特権が認められるかどうかは国によって考え方はまちまちであり統一的な見解はないという点である。国によっては、バンカー業者に先取特権を認める国と認めない国がある。
それでは上記のパナマ船の事例において、船舶先取特権の存在を認定する法律はどこの国の法律なのか?
船舶の船籍であるパナマの法律によって船舶先取特権の存在が認められなくてはならないのか?
バンカーが供給された国であるシンガポールの法律を検討する必要があるのか?
日本で差押をするのであるから日本の法律が判断基準になるのか?
バンカーの供給契約の準拠法である英国法が基礎になるのか?
この点に関しては、解釈が定まっておらず、裁判所によって判断がまちまちというのが現状である。
さきほどの香港の中堅のコンテナ会社の倒産事例であるが、筆者は差し押さえられた船会社の代理人として関与したが、この「判断する基礎となる法律はどこの国か」という議論を活用し、バンカー業者によって差し押さえられた8隻のうち、7隻は裁判により差押を取り消すことに成功した(1隻は和解で解決)。
OWバンカーの破綻により、元売り業者による我が国での船舶差押は避けられない状況であるが、差押においては、この「基礎となる法律が何処の国か」の議論が再び脚光を浴びることになると思われる。
業務内容
■海事紛争の解決
■海難事故・航空機事故の処理・海難事故(船舶衝突・油濁・座礁等)
■航空機事故
■海事契約に対するアドバイス
■諸外国での海事紛争の処理
■海事関係の税法問題におけるアドバイス
■船舶金融(シップファイナンス)
■海事倒産事件の処理・債権回収
■貿易・信用状をめぐる紛争処理 貿易あるいは信用状をめぐる紛争、石油やその他商品の売買取引をめぐる紛争を解決します。ICC仲裁やJCAA(日本商事仲裁協会)の仲裁も行ないます。Laytime、Demurrageに関してもアドバイスを行います。
■ヨット・プレジャーボートなどに関する法律問題 ヨット、プレジャーボートやジェットスキーなどの海難事故に対処するとともに、これらの売買などにかかわる法律問題に関してもアドヴァイスを行います。
■航空機ファイナンス(Aviation Finance)
免責事項
「海事法役に立つはなし」のコンテンツはマックス法律事務所殿から提供を受けているものです。よって、マリンネット(株)が作成するマーケットレポート等、オンライン又はオフラインによりマリンネット(株)が提供する情報の内容と異なる可能性があります。従いまして、マリンネット(株)は本「海事法役に立つはなし」の記載内容を保証するものではありません。もし記載内容が原因となり、関係者が損害を被る事態、又は利益を逸失する事態が起きても、マリンネット(株)はいかなる義務も責任も負いません
著作権
•マックス法律事務所が海事法 役に立つはなし(http://www.marine-net.com/maritimelaw/)に掲載している情報、写真および図表等全てのコンテンツの著作権は、マックス法律事務所、マリンネット、またはその他の情報提供者に帰属しています。
•著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、コンテンツの複製や要約、電子メディアや印刷物等の媒体への再利用・転用は、著作権法に触れる行為となります。
•「私的使用」1あるいは「引用」2の行為は著作権法で認められていますが、その範囲を超えコンテンツを利用する場合には、著作権者の使用許諾が必要となります。また、個人で行う場合であっても、ホームページやブログ、電子掲示板など不特定多数の人がアクセスまたは閲覧できる環境に記事、写真、図表等のコンテンツを晒すことは、私的使用の範囲を逸脱する行為となります。
1. 著作権法第30条 「著作物は、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」
2. 著作権法第32条 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
Email : info@marine-net.com
