 田渕海運株式会社
田渕海運株式会社
代表取締役社長 田渕 訓生 氏 ――LPG船、ケミカル船を中心に、石油化学輸送のパイオニアとして内航船・外航船事業を手掛けている田渕海運の田渕 訓生社長です。田渕海運の概要・特色についてご紹介いただけますでしょうか。
当社は1917年(大正6年)、貨物船による石炭輸送からスタートした会社です。戦後の1965年以降、エネルギー革命に伴う石炭から原油・石油製品への輸送貨物の転換を経て、今日では石油化学品輸送をメインに展開しています。外航船事業については1970年代に一時期、行っていましたが、1993年頃から本格的に進出しており、現在、売上の内訳は内航船、外航船で6対4程度です。――徐々に外航船事業の割合を伸ばしているのですね。
バブル崩壊で国内の経済成長に陰りが見え始めた頃、荷主さんの海外進出に伴って当社も外航船事業に本格進出を果たし、1995年当時には全体の1割程度だった外航船事業の売上が、現在では4割にまで成長しています。――内航船、外航船それぞれの事業概要についてお聞かせください。
内航船部門のうちLPG船に関しては、民生用・産業用いずれも燃料転換が進み、従来のLPG燃料主体の輸送から、石化LPG輸送メインにシフトしています。業界の25%弱を占める22隻を運航し、変化の激しい石化業界の輸送に対応するため、フリー船を多数保有しています。また同業他社とのバーター等を積極的に行うことで、顧客のニーズへの柔軟な対応が可能になっているほか、効率配船ができる点が当社の強みです。 内航ケミカル船については、専用船9隻、フリー船11隻の船隊構成です。フリー船は100種類程度の貨物を互換積みしており、様々な化学品輸送に対応しています。また2,200Dwt型(1,200総トン)の内外併用のフリー船2隻を投入し、当社独自の内外一貫輸送を行っています。このうち1隻は定温輸送が必要な特殊貨物であるプロピレン・オキサイド(PO)も輸送可能で、内航では唯一のPOのフリー船であり、輸送需要に応じて様々な顧客向けの輸送に従事しています。
内航ケミカル船については、専用船9隻、フリー船11隻の船隊構成です。フリー船は100種類程度の貨物を互換積みしており、様々な化学品輸送に対応しています。また2,200Dwt型(1,200総トン)の内外併用のフリー船2隻を投入し、当社独自の内外一貫輸送を行っています。このうち1隻は定温輸送が必要な特殊貨物であるプロピレン・オキサイド(PO)も輸送可能で、内航では唯一のPOのフリー船であり、輸送需要に応じて様々な顧客向けの輸送に従事しています。
外航船部門ではLPG船11隻(全てT/Cアウト)、ケミカル船10隻を運航しており、共通しているのは自社船・自社管理をベースに安全安定輸送を行っていることです。LPG船は、国内のバース規制に対応する3,500m3型を7隻保有している点が強みです。ケミカル船については、全てステンレス仕様でアジア域内での多品種・小ロット輸送に対応しているほか、POの積載が可能な船腹で構成している点が特色です。また、危険性の高い濃硝酸輸送に対応したIMO資格のタイプIを有する船腹も保有しています。――内航船の船員不足について、業界内で長年にわたって問題提起をされていらっしゃいます。
特に小型船は大型船に比べて運航効率が低く、運賃水準が相対的に低くなってしまうことから、船員費に多くを充てづらい状況です。加えて、小型船の方が荒天時の揺れや船酔いがきついこともあり、若手の確保が難しいほか、少人数運航で夜間の監視業務を1人で行うため、人材の育成も進みづらいという課題があります。小型船では勤務時間にゆとりがないため、中堅の船員も若手を指導する役割を敬遠し、大型船を志向する傾向もあります。――内航船員の高齢化の問題も指摘されて久しいです。
石油製品の内航タンカーで船員の平均年齢が45歳程度となっているのに対し、ケミカル船では、数年前と比べるとやや若齢化していますが、それでも50歳を超えているのが現状です。
――特に内航ケミカル船に船員が集まりにくい背景には何があるのでしょうか。
ケミカル船では積載する貨物が100種類程度にのぼり、航海毎にカーゴタンクを洗浄する必要があることが一因です。1隻の船に同じ貨物を積んで専用船にすればタンククリーニングは不要になりますが、化学品は基本的に多品種・小ロットで、1隻分に満たない数種類の貨物を同時に輸送することになり、クリーニングなしでは次航海の貨物を積むことができません。貨物によってクリーニングの手順は異なりますが、バターワース洗浄機での清水洗浄や洗剤洗浄後、最後に船員がタンク内に入って残液を拭き取る作業が発生する場合があります。当然、安全対策を施したうえではありますが、危険だと避けられてしまうことがあります。――船員不足問題のために内航ケミカル船の船隊の稼働率が低下している現状に対して、解決のためのキーワードはどのようなものでしょうか。
船型の「大型化」です。当社では2019年から2,200Dwt型を3隻運航しており、目下、順調に稼働しています。荷主さんからもロットアップにご協力いただいているうえに、当社独自のオペレーション、そして豊富な貨物バリエーションによって成り立っており、輸送効率の向上に貢献しています。船主さんからも、大型船の方が船員を集めやすく、またワッチも1人体制でなく済むために若手の育成がしやすいとお話をいただいています。フリー船で運航しており、荷主さんの数や貨物の種類、そしてオペレーション力無しには実現が難しく、当社でしかできない取り組みだと考えています。荷主さんの要望で建造するのであれば他社でも可能だと感じますが、フリー船をリプレースで大型化することは、かなりのリスクなのではと考えます。
――輸送の効率化・船員確保の両面でメリットのあるこのお取り組み、田渕海運さんだからこそなし得るのですね。
当社は荷主さんのロットサイズのご協力のもと、船型の大型化に踏み切りましたが、集荷の面以外にも、ケミカル船の主流船型は1,000Dwt(499総トン型)のため、大型船型では受入可能なバースが限られてしまう難しさがあります。加えて、陸上の規制の関係で、荷主さん側の受入タンクの容量の増強にも困難があります。現在の運航規模を飛躍的に拡大させるのは現実的ではないと感じます。――2022年3月、国内初のメタノール燃料内航ケミカル船の開発について、商船三井や商船三井内航、村上秀造船、新居浜海運、阪神内燃機工業と共同で発表されました。お取り組みの経緯についてお聞かせください。
当社は商船三井内航さんから共同船主の打診を受け、メタノール燃料主機関の開発に携わり、カーボンニュートラルへ貢献したいとの思いで今回の共同建造に着手しました。船舶管理や船員の配乗は当社が行います。
――メタノール燃料船への船員の配乗に当たり、特別な要件はあるのでしょうか。
積み荷としてのメタノールの輸送には従来から取り組んでいますが、メタノール燃料船の保有は新たな試みになります。メタノール燃料の知識を有し、取扱い方法や技術に習熟した船員を育成するため、研修を行っていく予定です。
――内航船の燃料転換についてのご見解をお聞かせください。
内航船の場合は、国土交通省海事局により、2030年までに2013年比でCO2を181万トン(約17%)削減する目標が策定されています。2023年以降、現状の省エネ船から、省エネ技術をさらに高度化した連携型省エネ船の普及が進んで行く見込みです。外航船と異なり、内航船では小規模の船主さんもいらっしゃいます。代替燃料仕様の高コストな船舶へのリプレースでは運賃の回収が難しく、現状では、既存の技術の導入で実現可能な手段でCO2の排出削減に取り組んでいくものと考えています。――注目している代替燃料や新技術にはどのようなものがありますでしょうか。
C重油に混ぜて使用するバイオ燃料は、主機関の改造なしに使用できるため低炭素の実現手段として有効である一方、価格や流通面では懸念も感じます。脱炭素化の解の一つとして、今後のCCS(CO2の回収・貯留)分野の技術の進展を注視しています。――代替燃料については、既存の主機関から大きく変わらないものをベースにお考えでしょうか。
今般のメタノール燃料内航ケミカル船に限らず、今後も代替燃料船には積極的に取り組んでいきたいと考えています。ただ一方、内航船はバンカリングの面で外航船とは異なります。日本ではLNG燃料ですら、シンガポールや韓国と比較してバンカリング拠点の整備が進んでおらず、外航船は外地でバンカリングを行うことになります。一方、内航船の場合では、国内での供給体制が整っていないことには、燃料転換は実現し得ません。しばらくの間は、連携型省エネ船で船型を絞るほか、省エネ運航で低炭素化に向けて対応していくことになると考えています。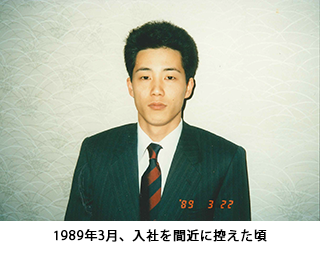
――印象に残っているお仕事についてお聞かせください。
2000年12月、先代社長を務めていた父親の永眠に伴い、35歳で社長に就任しました。その後、全国内航輸送海運組合の会長職にあった父親の組合活動を継承して活動を始めました。父親の在職時代、当社の主力事業の軸足が貨物船からタンカーに移っていき、全国内航タンカー海運組合(タンカー組合)をメインに、父親ほどの年齢の周囲にたった1人の若手として飛び込み、活動をスタートしました。
2004年、タンカー組合関西支部の支部長に就任(タンカー組合副会長を兼任)し、その後の2008年から2014年頃までの6年間、内航ケミカル連絡会の議長の仕事で多忙な毎日を過ごしました。この仕事は荷主さんの部長クラスに集まってもらい、内航ケミカル船の抱える諸問題をオペレーターや船主6社程度から提起する場です。――荷主さんに向けて、特に力を入れて訴えて来られたのが、「二つの高齢化問題」だそうですね。
冒頭でお話しした船員の高齢化に加えて、特殊な液体貨物を積むケミカル船は傷みが激しいことから、船舶の老齢化への対応も講じる必要があります。早めのリプレースを行うに当たり、コストアップ分を運賃の面でご協力いただくべく、荷主さんにお願いして来ました。当社に対する荷主さんの印象をダウンさせ、営業担当の社員に迷惑が掛かることのないように言葉を選んで伝えるなど、議長職は緊張する役回りでした。ただ、必死になって対応すると誠意が伝わったのか、ご理解をいただけたことが印象深いです。――ご苦労も多かったと思いますが、業界の取りまとめをご経験されて良かった点としては?
オペレーターや船主側で共通する悩み事を荷主さんに訴える場として、業界内で結束できたことです。しんどいことも多いですが、「田渕さん頑張ってるね」と声を掛けていただき、共感してくださる方々に恵まれ、内部に友人が増えました。現在も議長職に就いています。――人生の転機となった事柄についてお聞かせください。
まず一つ目は、35歳で社長に就任したことです。それまでは、当時の常務と一緒に営業で荷主さん回りを担当していましたが、その当時に想像していた社長のイメージと少し違い、いざ着任してみると、本当の社長の重みをひしひしと感じました。
二つ目は、2017年に日本内航海運組合総連合会の理事に就任し、同時にタンカー組合から選出される環境安全委員長に就任したことです。2018年からはSOx対策委員長も兼任しており、技術系出身ではない自分が業界屈指の技術屋集団をまとめ上げることができるのか、最初は不安の連続でしたが、何とかこなして現在に至っています。この経験を通じ、技術系でないからあきらめるのではなく、勉強すれば成果はついてくるということ、そして社長になってからでも努力次第で決して遅くはない、ということを実感しています。
――学んだすぐ後に、アウトプットする貴重な場があるのですね。
委員会付属の外部会議でも、業界の重鎮の方々がたくさんいらっしゃいます。50歳を過ぎてから新たに飛び込んだ世界ではありますが、自分に喝を入れることができて良かったのかも知れません。苦労の連続ではありますが、今では逆に楽しんで頑張っています。――座右の銘についてご紹介をお願いいたします。
若い頃は「七転び八起き」をモットーに奮闘していましたが、現在57歳ですので、これからは転ぶことのないように、自己研鑽を積んで「深い川は静かに流れる」ように悠然とありたいと考えています。また、苦しい時には「待てば海路の日和あり」の気持ちで頑張りたいと思っています。――最近感動したことについてお聞かせください。
新型コロナで自宅にいる時間が増え、YouTubeで様々な情報が得られることを知って、世界が広がったと感じます。映画やお笑いコンテンツを見るのも良いですが、ウクライナ情勢などの時事トピックから政治問題の対談まで、とても勉強になります。これからの人生で深く学ぶうえで、若者にならいこうした手段も活用していきたいと思います。――夢や目標について教えてください。
息子が2人おり、長男は当社に入社して大阪本社で働いています。次男は就職後、そんな兄の姿を見て自分も一緒に会社を手伝いたいということで、現在海運の世界で修行中です。――船会社は24時間体制ですが、お父様の背中をご覧になり、兄弟で会社を支えていきたいとお考えなのですね。
目標としては、長男には内航船部門とその他諸々、次男には外航船部門と兄弟で担当分野を分けてリーダーシップを発揮してもらいたいと考えており、それぞれ専門的に教育しているところです。
――思い出に残っている「一皿」についてご紹介ください。
大阪・弁天町の駅前の「博多っ娘」というお店の看板メニューは博多ラーメン、そしてなぜか長崎ちゃんぽんです。ただ、私のお気に入りは何と言っても博多皿うどんでなのです。パリパリの細麺ではなく柔らかい麺を焼き付けてあり、まさに感動の「一皿」です。――地域で愛されている名店なのですね。
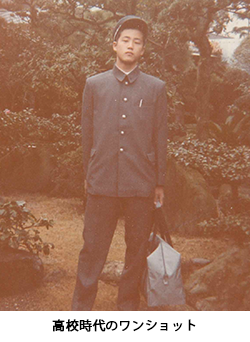
――学生の頃の思い出の味はありますでしょうか。
関西大学在学当時、大学の正門の辺りに「ギャルソン」という喫茶店がありました。チャーハンや焼きそば、スパゲティなど何でも気前良く大盛りサイズで、学生に大人気でした。懐かしい思い出です。――心に残る「絶景」についてお聞かせください。
新型コロナの感染拡大前は、現地オフィスのTABUCHI Marineを置いていることもあり、シンガポールには年に3,4回ほど行っていました。2018年、プライベートの休暇を兼ねて行った際、週末にシンガポール本島側からセントーサ島の遊園地に向けてロープウェイに乗りました。ビルの8階ほどの高さから出発して、海の上へとどんどん高度が上がっていくのです。高所恐怖症なので死にかけました(笑)。
――私も高いところは余り得意ではありませんが、それでも比較的楽しめる範囲かと感じましたが・・?
乗っている間ずっと、体はこわばり足はすくみっぱなしでした。絶景ではなく「絶叫」ですね(笑)。